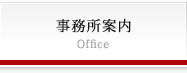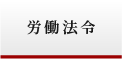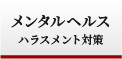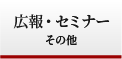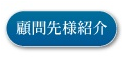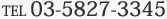【顧問先様紹介】~ 株式会社 伊豆榮 様 ~
2025年08月19日
顧問先様紹介

会 社 名 株式会社 伊豆榮
所 在 地 東京都台東区上野2-12-22
代 表 者 代表取締役社長 土肥 好美
法人設立 1950年9月22日
事業内容 鰻割烹及び日本料理の提供
会社HP https://izuei.co.jp/
弊社とは長くお付き合いいただいておりますが、
人事労務面についてあらためてお話を聞かせていただきました。
女将(社長)、女将(社長)を支える管理職の方、これからの伊豆榮様を支えていく方々から貴重なお話を聞くことができました。伊豆榮様を形成するDNAや文化が少しみえたような気がいたします。
そんな貴重なお話を少しご紹介できればと思います。
まずお一人目は、伊豆榮で複数の店舗のご経験をされている営業本部長、佐藤さんにお話を伺いました。

■プロフィール
佐藤さま 営業本部長
ご出身が上野の桜木とのことで、七五三の時に伊豆榮で食事をしていたというご縁もあるとのこと。今年で入社して17年になり、複数の店舗での勤務経験もある伊豆榮様のことをよく知るエース人財です。
ご趣味は、学生時代から嗜まれている“ベースギター”と将棋とのことで、きっと仕事にも活かされているのではないかと思われます。
(披露宴や会食の席など)お客様の様々なシチュエーションに合ったものをご提案、ご提供するところです。大変ですけれど、喜んでいただけたりするとそれが醍醐味に繋がります。
いっぱいありましたけど、どれもいい思い出です(笑)。
正直あります。何度も。
自身のミスが原因で上司から怒られたときとか、凄く悔しかったときとかに。
でも、それを改善して今があるのだと思います。それの繰り返しですね。
あと怒られたときに皆が慰めてくれるんです。皆に支えられています。
- なるほど、この会社の雰囲気や仲間がいるから続けてこられたのだと感じました。
「お店を好きになってくれる人」です。
梅川亭は上野公園の中にありますし、お店は上野と一体化しています。そういう意味では、上野も含めて愛してくれる人が良いと思います。

〔 生まれてからずっと上野で過ごしていて、伝統のあるこの街で働けるのが嬉しいとのこと 〕
いやもう十分です(笑いながら)。
それはもういっぱいいます。うちは年齢幅が広いので、各年代にいます。
私自身熱い性格なので、だからこそ一度よく考えてから、対応するように気をつけています。
もっと若い人が入社してきてほしいですね。
飲食店の大変さなどから就職をためらう人が多くなってきていることもありますが、労働環境等も変わってきていますので、若い人にもぜひチャレンジして楽しさを分かってほしいと思います。
いろいろ抱えこんでしまうと大変になってしまうから、もっと下の人たちに(技術や知識などを)伝えてあげてほしいと思います。
もっといろいろ覚えて欲しいです。そうすれば、もっと仕事が楽しくなると思います。
普段から伝えていますけど、あらためて言うなら健康を崩さないように過ごしてほしいです。
女将(社長)のような、明るい、華のある会社(お店)です。
また、昨今は外国人のお客様も増えてきたり、時代に合わせて色々変えていかなければならないところがありますが、伝統は守らなければならないと考えています。
伝統を守ることは人を守ることにも繋がりますから、“上野に伊豆榮あり”ではありませんけれど、そういう大事なものを守っていけている会社だなと思います。
続いて、厨房で調理を担当している蘇さんにお話を伺いました
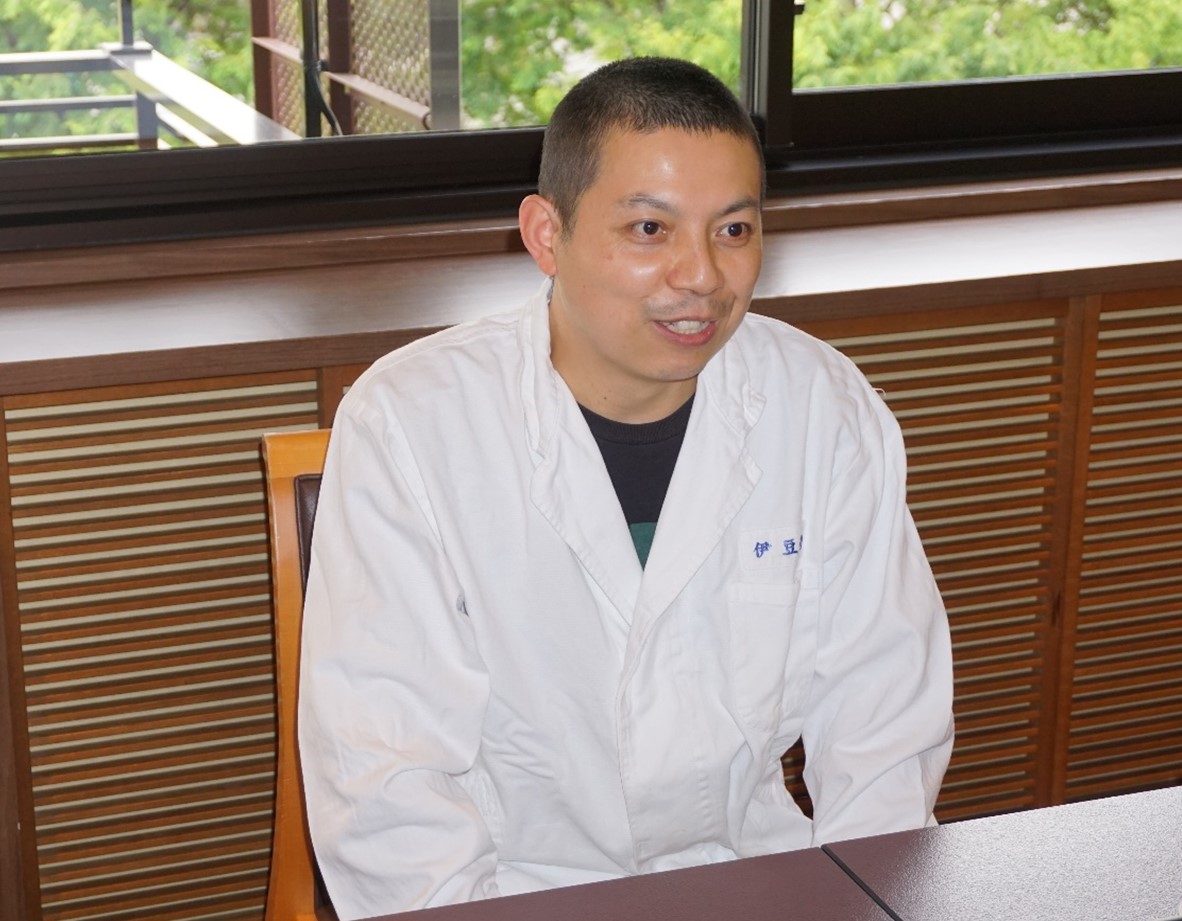
■プロフィール
蘇さま 調理担当
料理人の蘇さん。日本料理は難しいとお話しされていましたが、もう入社して9年になる中核社員です。
休みの日は散歩やランニングをしていて、駅でいうと4~5駅くらいの距離は平気とのこと。体力、健康面でも自信がある方で、伊豆榮さまにとっては、今後を担うまさにホープ調理人です。
① 具体的にどのような調理をされているのですか?
魚をおろす、料理の盛り付け、仕込み、全部やっています。
和食は難しい。けど頑張っています。
和食料理ができることも、仕事仲間と楽しく仕事ができることも、いっぱいあります。
ありません。すごい楽しい。みんな優しいので。
みんなが一緒に楽しく仲良く仕事できるところです。

もちろん、そうです!
用事があるときは、調整してもらって長い休みが取れます。
また、プライベートなことについても親身になって応えてくれる本当に頼りになるところです。
女将(社長)さんも入社からずっと優しいです。
三人目は、伊豆榮さまの人事労務責任者の佐々木様にお話を伺いました。

■プロフィール
佐々木さま 人事労務責任者
弊社との接点も一番多い大変お世話になっている方です。
ご趣味も、写真やピアノとのことですが、その造詣は深いものがあります。
ここで培われた深い洞察力や広い視野が、伊豆榮様の大事な人事教育などにもきっと活かされていることと思われます。
女将(社長)からの信頼も厚く、伊豆榮様の運営管理の重責を担っている方です。
① 伊豆榮さんは教育制度にも力を入れていますが、どんなものか簡単におしえてください。
基本的には2つ用意しています。まずは入社1週間研修、そして3年目研修があります。
外国籍の従業員が多かった時は、それに伴う講座も受けてもらいます。
うちの研修では最後にウナギの話をします。ウナギの生体から、伊豆榮の料理になるまでの過程を知ってもらうためです。
また、それだけではなく、この先の業界の話までを含めて伝えています。
③ 会社の雰囲気はどのように感じていますか?
日頃のコミュニケーションがしっかりとれていると思います。
みんな切磋琢磨していて、(社内風土的に)優劣などはつけたりしていません。
調理場に足を運んでも本当に楽しい雰囲気を感じます。
特に挙げるとすれば、若い人が長く続けてもらえるかどうかですね。
今の若い人はすぐ辞めてしまう傾向があるのですけど、せっかくの機会を得たわけですから、スキルや経験を身に着けてからでもいいのではないかと思います。
⑤ その課題に対して、何か具体的な取り組みなどがありますか?
協調性を学んでもらうように努めています。
後輩ができたときに責任感を抱くと思いますが、それとともにモチベーションも上がるので、毎年できれば新卒の人を採用するように努めています。
いろいろありましたけど…。ウナギが不漁になった時は大変でしたね。
仕入れはうまくいかなくなるし、価格は高騰するしで…。
― 伊豆榮さんは国産ウナギにこだわっていらっしゃいますし、それはとても大変でしたね。
そんな状況で、女将(社長)も落ち込んでいましたから、(仕入れ担当ではない自分の立場でも)何ができるかなと考えたんです。
そこで各県の養鰻場に自社の状況を綴った手紙を手書きで書いて送ったんです。
そうしたら名乗りをあげてくださった会社(養鰻場)があったので、実際に女将(社長)とともに足を運びました。後日、その会社(養鰻場)の社長から手紙が届きまして、「限界までウナギを供給します」って約束してくれたんです。この会社さんとは今でもやり取りさせてもらっています。
大変なことも何らかの突破口があるんじゃないかと考えて、いつも足を動かしています。
従業員への待遇を良くしたいです。それができれば更に離職率も減ってくるのではと思っています。
特に若い人でも安定して生活ができるような環境を会社側がバックアップしていければ、次の世代、次の次の世代までが会社に入社してくれると考えています。
人それぞれ持ち味があるから存分に発揮して欲しいです。
それだけではうまくいかないので、皆が協調性をもって、それぞれの才能を活かせるといいなと思います。
そんな会社になるように皆で協力してもっと良い会社にしていきましょう。
なかなか休みをとってくれないので、それが心配です。
まとまったお休みをとって旅行にでも行ったりしてほしいです。
とにかく倒れられたら困ります。
優しくて人の気持ちがよくわかる人です。
仕事の内容は、実際にやって覚えていけばいいと思っています。
人柄や人間性をよくみて採用しています。
― だから蘇さんのようにみんないい人が集まっているのですね。そう感じます。

最後に9代目女将、土肥 好美社長にお話をお伺いしました。

『素直な人』ですね。
そういう人は年齢に関係なく人の話を聞いてくれます。そうすることで自分を鑑みることもできますし、間違っていることを認めることができるようになります。
そんな人に一緒に働いて欲しいです。
私自身が毎日失敗だらけなので、経営者であっても同じ人間ですから。
私自身素直に捉えられるよう心掛けています。そうでなければ間違いを正せませんし、人間にとって一生の課題だと思います。
幸せになってほしいです。
私が毎日思っていることは、『商売繁盛と皆の幸せ』です。
皆幸せになるために働いているはずです。もちろん、お金を得るためには楽しいことも大変なこともあります。
経営者も、皆で幸せになろうよって思っている人が多いと思います。
そう考えています。
やはり、労働時間の管理が難しいと感じています。
前職ではOLをしていて、そこでは契約社員の当番表を作成していました。契約社員の労働時間は決まっていましたから、少しでも残業させまいと(私が)仕事を受け入れて後処理をしていました。とても大変だったのを覚えています。
それは伊豆榮でも同じで、昔はお休みが十分ではありませんでしたし、従業員に長時間労働させているのが当たり前でした。
そんな状態を目の当たりにして、社員に普通にお休みを取らせるようにしていったのです。
特にコロナをきっかけに大幅に改革することができました。コロナ前はあまり余暇が取れないお店がありましたが、そこは定休日をつくって無理矢理休みを取らせました。
もちろん売り上げは下がりますけれど、その中で利益率をあげていかなければなりません。その為に催事やテナントも撤退しました。
商いのやりかたは時代に合わせて変えていかなければなりません。
いつも“今”やらなきゃいけないことを考えています。
― 女将(社長)の声が従業員の皆に浸透していると感じました。
他の従業員の皆さんも女将(社長)の代になって大きく変わったといっていました。
ベテランも新人も、誰が(料理を)盛り付けても同じものを提供できるようにしなければいけないですし、(若い人のスキルを)底上げをしていかなければなりません。
ベテラン組が頑張ってくれていることにも感謝しています。
色んな事に取り組んで、もっと定着率をよくできたらいいなと思っています。

― 経営者は労働法令についてきちんと知っていなければならないと断言する女将(社長) ―
〔 ご自身自らも「衛生管理者」の資格を取得されるほどの有言実行の人です。 〕
“冬は必ず春となる”です。
絶対に春にならない冬はないので、頑張らなければならないと思います。
今特に頑張らなければと考えているのは『教育』です。
読み書きそろばんという意味ではなく、「礼に始まり礼に終わる」というように、人としての教育をしていかなければならないと考えています。
今の日本は職人の培ってきた技術や頭脳を継承していかなければいけないのに、それを教えていける人たちも少ない状況です。
上野は伝統の町です。『本物』って全然違うんですよ。着物も、草履も。
その『本物』を残していくために考えなければなりません。
これから日本の未来を背負っている人たちに、色んなことを教えてあげられたらいいなと思っています。

(社員全員に)『うちで働いてくれてありがとう』と言いたいです。
コロナの影響でお店を営業できなかった時でも、うちは職人が1人も辞めなかったんですよ。
皆が働いてくれるから商いができるんです。
― 女将(社長)が従業員の皆に本当に感謝されているという姿勢が感じられました。
そうですね。やはり労働時間の管理が難しいので、そういう労務管理面のことをもっと教えてほしいです。
また、どこまでが“パワハラ”にあたる…とか(指導との線引きなど)。
― 今後とも伊豆榮様に合った内容のものをご提案させていただければと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。
お互い相手を思いやれる会社だと思います。
結局のところ会社と労働者が交わるところはないのかと思います。でもそれを極限近い所にまでもっていきたいです。
先代も「職人は道具じゃない」と言っていましたが、とにかく“人”が大事です。
それぞれに役割があるにせよ、皆がお互いを思いやれる会社が『いい会社』だと考えます。
撮影ご協力 佐々木さま 聞き手 矢口
インタビュー中、女将(社長)は、「働いてくださる方がいるから、商いができるんです。」と重ね重ね言葉を発せられていました。
またインタビューを受けていただいた社員の皆様方からも女将(社長)に対する感謝や労いの言葉がたくさん出てきました。
労働者と経営者の信頼関係が成り立っている会社であることが特に感じられました。この信頼関係を基に伝統と革新の融合を考えながら、これからも伊豆榮様としての人事労務管理、教育体制などがより充実していくことと思われます。
またもう一つ大きいのは、女将(社長)の情熱です。社員の方々への「思いやり」や「素直な姿勢」が現場だけでなくいろいろな方面でも実際に行っているからこそ、皆との絆が深いものになっていると思います。
そして、労働働法令を理解することも時代に合せる人事施策であることを認識されている伊豆榮さまは強いと感じられました。我々も益々ご発展される伊豆榮様の一助になれればと切に願います。
最後になりますが、お忙しい中インタビューに快く応じてくださった皆さま、本当にありがとうございました。皆さまの率直な言葉が、多くの読者の心に届くと信じています。